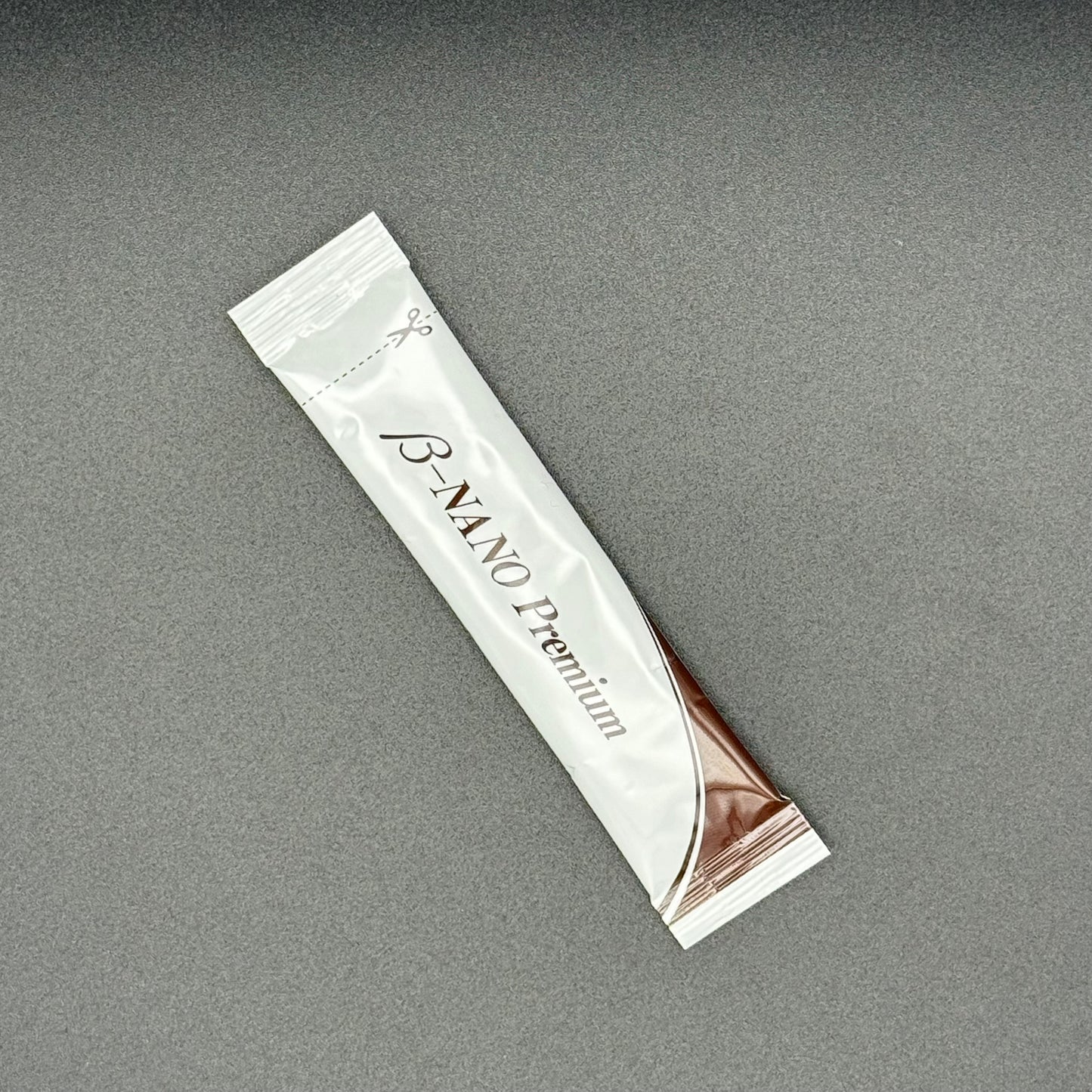β-グルカン β-GLUCAN
βグルカンとは?

グルカン
※グルコースは糖鎖栄養素の8単糖の内のひとつ
※グルコースが2つだけ連なったのがブドウ糖、10個ほど連なったのがオリゴ糖です。
多糖体のグルカンはエネルギー源には成らず、ゼロカロリーです。
つまりグルカンとはグルコースだけで連なった多糖体(分子学上は、10以上であれば多糖体)の総称で良く聞くβグルカンやセルロース、トレハロースなど、全てを束ねた呼び方です。
そのグルカンの中でグルコース分子のつながりがα型のものをαグルカン β型のつながりをもつものを「β(ベータ)グルカン」と分類されています。
β-グルカン
植物や菌類、細菌など自然界に広く分布しますが、アガリクスや霊芝などに含まれるβグルカンは主鎖1に分岐3の分子構造をもつ「β1.3グルカン」と呼ばれ、高い機能性を持つものとして1990年ごろから注目が集まってきました。
β1,4グルカンが由来に関係なく全てセルロースという名前を持つのに対し、β1,3グルカンは由来によって様々な名前が与えられています。
またβグルカンと言った時には通常β1,3-グルカンのことを指しますが先にのべた機能性をまったく持たないセルロース(β1,4グルカン)なども、科学的な分析ではすべてβグルカンとして計測されてしまうので、食品(健康食品を含む)の栄養表示にあるβグルカンすべてをβ1.3グルカンだと誤認しないように注意が必要です。
現在、βグルカンの中でも、もっとも機能性が確かで注目されているのは「β1.3-1.6グルカン」です。
βグルカンはそのカタカナの呼び名が示す通り元々アメリカで発見された物質です。
水溶性と耐水性(難水溶性)と不溶性
【水溶性】とは・・
物質が水にとけて水溶液をつくる性質のこと。
その程度を表すのに、易溶・可溶・微溶・難溶・不溶の言葉が使われます。
【溶解】
溶けること。また、溶かすこと。特に、気体・液体・固体が他の液体あるいは固体と混合して均一な状態となる現象。
ふつうは、各種物質が液体に溶けて溶液となることをいう。
水溶性βグルカンと可溶性βグルカンと不溶性βグルカン
一般に、気圧1、温度20度の水の状態で溶かした場合、均一に溶液に広がった(沈殿、分離が無く)状態を指します。
βグルカンの場合は「食物繊維」なので、完全に溶解した場合と半溶解した場合では光の屈折度が違うことで判断できます。
| βグルカンが分析で 含有される素材 |
結合の種類 | 糖鎖の有無 | 機能性の高さ | 水溶性 | 吸収性 |
| セルロース | β1.4結合 | 無 | 無 | 不溶 | 不可 |
| ハナビラタケ | β1.3グルカン | 原材料 には有 |
低 | 難溶 | △ |
| 大麦 | β1.3-1.4 グルカン |
原材料 には微量有 |
低 | 可溶 | △ |
| アガリクス (※ラミナラン) |
β1.3-1.6 グルカン |
原材料 には有 |
中 | 可溶 | △ |
| パン酵母抽出物 | β1.3グルカン ※3分の1に1.6結合あり |
無(原材料 には有) |
低 | 不溶 | 不可 |
| 黒酵母発酵液 | β1.3-1.6 グルカン |
有 | 高 | 易溶 | ○ |
※ラミナラン
β1-3結合とβ1-6結合のグルコース主鎖からなる直鎖の多糖で、β1-3結合とβ1-6結合の比は約3:1
機能性が最も高いのは「β1.3-1.6グルカン」
ついで、ラミナランなどの三分の一に1.6グルカンがついたもの。
以下、β1.3グルカンとなり、β1.4グルカンは機能性はありません。
また多糖類(高分子)なので、水溶解性が弱いと吸収が悪いのも機能性に影響します。
また近年の研究で「81.3グルカン」を有しても、それだけでは機能性が低いということが分かってきました。アガリクスでもそうですが、「全体を食す」ことで「糖鎖栄養素」を同時に摂取します。
それが体内で有機的に機能し特性を発揮していたと考えられます。つまりβグルカン単体の抽出製品は機能性をわざわざ弱くしていたということです。
何でも、抽出して他の成分を除去し高濃度にすれば機能性が高まると考えている化学の盲点だといえます。
β-グルカンの名前の由来と研究の歴史
61,3グルカンもアメリカの研究陣
(米Tulane医科大学のNicholas DiLuzio博士〔1926-1986)等の研究陣だと言われています)が酵母細胞壁から発見した,糖質分子(六単糖、Hexose)が1->3方向で水素結合した3重螺旋構造の鎖状物質を名づけた言葉です。
炭素配置の右回転方向を表す”D"を加えて、日本ではβ1,3Dグルカンと呼ばれることもあります。
糖の分子が1->3結合だけではなく、酵母細胞壁からβグルカンへの分離抽出過程で1->6方向で水素結合した、いわゆるβ1,6グルカンと呼ばれる分子の鎖もわずかに残るため、日本ではβ1.3-1.6グルカンなどと呼ばれることもあります。
このことから、βグルカンは通常は「β1.3グルカン」を指しますが「β1.3グルカン」を含有した食品(健康食品)を「β1.3-1.6グルカン含有」と表示しても法的な問題はありません。
が、通常市販されている食品(健康食品を含む)、アガリクス、レイシ(霊芝)、パン酵母などに含まれるβ1.3グルカンは、ほとんど分岐1.6の分子の鎖を持ちませんので注意が必要です。

アガリクス
健康食品の素材として定番のアガリクスとは、ブラジルが原産のキノコです。豊富な栄養成分が含まれており、なかでも高分子多糖体β-1.3グルカンの含有量は他のキノコ類と比べた場合、非常に多いのが特徴です。
アガリクスの品種の中でも「姫マツタケ」と呼ばれるキノコ(学名:岩出101株)に含まれる
βグルカンは主鎖1.3分岐1.6の β1.3-1.6グルカンを多く含むことから希少価値がうまれ、比較的高価で取引されています。
当社が推奨する黒酵母から産生されるβグルカンの特徴のひとつは含まれるβグルカンのほとんどの分子構造が、このβ1.3-1.6グルカンであることです。
β(ベータ)グルカンを含む通常の食品
キノコ類
〇アガリクス〇霊芝〇まいたけ〇しいたけ〇エリンギ〇なめこ〇ひらたけ
穀類
〇オーツ麦
: 〇大麦
β-グルカンの歴史は結構長い
米国などでは機能性研究対象となっているのは酵母
saccharomyces cerevisiae(いわゆるイースト菌やビール酵母)の細胞壁から抽出されたβ1,3グルカンであることが多くみられます。
世界的にみて西洋文化の国の主食の多くは小麦であり、パンである事が多くその食文化の中から生まれた研究であることが初の理由であると考えられます。
また原料母体となる酵母(パン酵母、ビール酵母等)は世界各国で数千年にわたる食菌としての歴史に支えられて相当量が確保できるからです。
そこから抽出されるベータ1,3Dグルカンという物質が生体に及ぼす機能性についても相当数の実験結果があります。
一方において現在、酵母から抽出されるベータ1,3Dグルカンという物質の特定とその物質の及ぼす作用機序については未知な部分が多く、さらなる特定方法と定量分析方法の早期確立、統計的実験以外にヒトを対象とした実際の経時による安全性と作用機序の立証などが望まれています。
サイトでご紹介している黒酵母発酵液は上記のパン酵母やビール酵母などとは違いまた食菌としての歴史がなく、発見されたのが日本なので発見、研究が始められてまだ30年であること。
まだ世界的には認知度が低いことなどが原因で、研究も日本国内企業が最先端の状態です。
科学では世界最先端の我国内で発見、研究、そして世界をリードしていく素材であることは日本人として大変嬉しい事です。
黒酵母発酵液から産生された水溶性βグルカン
(アルコール抽出させて目に見えるようにしたもの)
また近年の研究で”βグルカン単独”での機能性は当初期待されていたほどでは無いという事が徐々に分かってきました。
と、いうよりも自然界に元々β-グルカン単独のものはなく霊芝にしても、アガリクスにしてもβ-グルカンを含んだ食品全体が「良い」のに西洋文化の今までの流れで、”当然、抽出して単独の高濃度にしたものが良いに決っている”と人間が勝手に決めつけた先入観が、現在の間違いを生んでしまったといえます。
糖鎖の研究の中で、β-グルカンは糖鎖栄養素と関連している事が分かってきました。
思えば、キノコもβ-グルカンだけでなく、その食物繊維の中に豊富な糖鎖栄養素も同時に含みそれ全体を食して、健康に良かったのです。
これからはβ-グルカン+糖鎖
まだまだ分からない事が多いβ-グルカンや糖鎖ですが、人間の寿命が限られている限りあと50年、100年も待つわけにはいきません。
現時点では、優秀なβーグルカンと糖鎖栄養素の連携での健康管理が望ましいと考えられます。
現在まで他のβグルカン単独の抽出素材よりも、黒酵母が優位的な機能性を発揮していたのはそのβグルカンの優秀さであると考えられていましたが、どうやらそれだけでなくこの複合糖鎖との統合的な機能性が原因であるということが分かってきたからです。
当社がフコイダンと双璧に黒酵母発酵液を推奨するのは
優秀なβグルカンだけでなく「複合糖鎖」と呼ばれる糖鎖栄養素も豊富に含まれているからです。
良いβ-グルカンの選び方